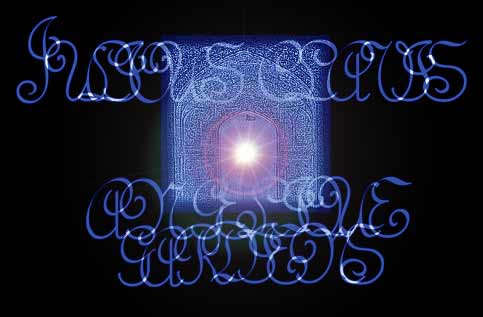|
この後、ジュリアスが聖地を去ったのは、聖地時間で一年の後、
クラヴィスの世界では、十年近い歳月が流れていた。
いつもと変わらない午後の祈りだけが響く寺院の中で、次元回廊が秘かに、また開く。が、下界に降り立ち、人として十年を過ごしたクラヴィスには、次元回廊は見えもせず、その気配を感じることも出来ない。
「午後の祈祷が始まりましたよ、クラヴィスさんも休憩にしませんか?」
若い学者の一人に声を掛けられたクラヴィスは、書き物をしていた手を止めた。この十年の間に彼が、タイルから読みとった膨大な叙事文、祈祷文の編纂は終盤を迎えようとしていた。朝から日の落ちるまで、丹念にタイルに描かれた絵や文字を写し取り訳す作業を、根気よく続けていた。お茶を飲みながら雑談を交わしている者たちの輪に、クラヴィスは今日は加わらずに立ち上がった。
中庭を通り過ぎる風に吹かれたいと、ふと思ったのは、強い午後の日差しに渇きを覚えたか、あるいは……。
部屋を出たクラヴィスは、祈りの邪魔にならぬように静かに、薄暗い回廊を抜け、光差す中庭に向かった。青いタイルに守られた屋内から中庭を見渡せる外廊下に出ると、のたうつような暑熱がクラヴィスを襲った。ただ、一点、風の通るように計算された柱の影に立ち、彼は揺らめく陽炎を見続けた。その中に、時々垣間見る追想に身を任せたい欲望に駆られて。
簡素な衣服に身を包んだジュリアスが立っている幻影が見えた。これまでも何度かそういう幻をクラヴィスは見ていた。それは、ジュリアスだけでなく、ルヴァであったり、リュミエールだったこともあった。この地方で行われる祭りの剣士役の姿に、オスカーを思い出すこともあれば、子どもたちのはしゃぐ姿が、ランディやゼフェルたちの姿と重ることもあった。緑の木々の合間や、どこから飛んできた蝶に、マルセルやオリヴィエの姿を垣間見ることさえもあった。それはいつも、瞬きの合間にかき消えるはずのものだった。
しかし、今日のジュリアスの幻は、いつまでたっても消えずに陽炎の中で揺れていた。
「早く出迎えぬか、暑くて倒れてしまうぞ」
幻が、喋った。
「勝手に入ればよかろう」
幻だと思っているモノに向かって、クラヴィスは返事をした。そう言いながら涙が滲んだ。今度も……あの幻は、午後の日差しが造り出す大きな陰に、飲み込まれて消えてしまうのだろう、と思いながら、クラヴィスは、瞳を閉じて涙が乾くのを待った。
次第に近づいてくる足音と、微かに拭く風に乗って漂う懐かしい薫りが、それが幻であることを否定していた。
何故、来たのか、とクラヴィスは問わなかった。ジュリアスも待っていたかとは、聞かなかった。再び共有できる長い時の中で、その答えは自ずと出されると、二人は知っていた。
かつて、二人を繋いでいた聖地も、サクリアも、もう無い。同じ思い出を持つ古い友人たちが、静かに再会を果たしただけであると、二人は、ごく自然にそれを感じていた。
ともに生まれ、ともに消えてゆく……その光と闇の摂理に、今はただ感謝しながら、二人は微笑みあった。
終
|