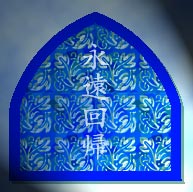「奥に進むほどに青の色が増して行く……外の乾いた世界からよほど遮断したかったらしいな」
ジュリアスは、周囲を見回しながら言った。
「この地にあっては、灼熱が第一の敵、それを遮る術のある者ほど、身分が高いとされてきた。権力の誇示、その固まりだな、この宮は……」
クラヴィスの言葉には、この宮を建てた者への侮蔑が含まれていた、そして悲しみも。
二人がさらに奥へと進もうとした、その刹那、鐘の音が数回鳴った。その余韻の中から、低い声が、幾重にも合わさって響いてきた。
「午後の祈りが始まったのか……」
ジュリアスが、横手に拡がった大きな部屋の中をそっと覗き見ると、黒いヴェールをまとった数人の僧が傅き、祈りを捧げていた。その部屋も、何もかもが青かった。壁も天井も床も。ただ僧侶たちの衣だけが、影のように黒かった。
部屋の入口でジュリアスは、またクラヴィスに尋ねた。
「ここではないのか?」
「違う……」
クラヴィスが呟くと、ジュリアスは頷き、祈祷の声を聞きながら、さらに奥へと進んだ。幾つもの小部屋を従えた回廊の、さらに奥を目指してジュリアスとクラヴィスは進む。
(魂の嘆きはどこに巣くっているのだろう……)
とジュリアスは五感を張り巡らせてみる。だが、感じられるのは、古の建物と祈りが造り出す荘厳な雰囲気だけである。回廊の随所、丁度、ジュリアスの目の高さほどの位置に、小さなレリーフが埋め込まれた箇所があり、ジュリアスは観光でここに来たのではないと判っていても、ついそれらに目を奪われながら歩いていた。王族の姿を写し取ったと思われるもの、何かの守り神なのか半身が獣のもの、女神のようなもの、長い歳月に晒され風化されてはいるものの、いずれも作り手の想いが、まだ息づいているかのようだった。
ふと、クラヴィスは、レリーフのひとつに足を止めた。自分とよく似た長い髪の女が優雅に舞っている踊り子の姿に、懐かしいものを見た気がしたのだ。
(まさか……な)
と否定しながらも、もしやそれは我が母の姿では、と思ったのだった。旅芸人の一行は、よく王宮に招かれた。殊に母は王の寵愛をも受けていた。自分という子を成すほどに……。
クラヴィスは、もう一度だけレリーフの踊り子を見てから、ジュリアスの後を追った。時間にして僅か数十秒のことであるのに、クラヴィスは角を曲がったところにジュリアスの姿を見つけられなかった。ほんの少し先に、上の階に続くと思われる短い階段があり、クラヴィスはそこに急いだ。案内板もその階段を進むようにと指示していた。が、その時、上部にある灯り取りの窓から少し日差しが、差し込んできた。ふと見ると階段の横手、行き止まりと思っていた暗い所に、先に続く細い廊下が見えた。
「こんなところに回廊が続いていたのか……」
クラヴィスは、明らかに自分の探している場所が、そちらに続いていると確信すると、その中を覗いてみた。回廊はだんだん狭く薄暗くなっているようだった。
ジュリアスは、案内板の指示に従い階段を上がって行ったに違いないとクラヴィスは思ったが、探しに行こうとせず、その薄暗い回廊の中に入って行った。
どうせ後ろにいないことが判るとジュリアスは引き返して来て、この回廊を見つけるだろう、とクラヴィスは思ったのだった。
クラヴィスは横道には逸れず、回廊の両端にある小部屋にも入らずにただ、真っ直ぐに歩いた。狭い回廊が広くなったことに安堵を覚えたクラヴィスは、目の前に、王家の紋章の入った鉄のプレートを見つけて、その方向に歩き出した。さらに回廊は続く。それは人にはあまり感じられないほどの微かな勾配で作られたもので、クラヴィス本人は、ただ真っ直ぐに歩いているだけのつもりだったが、僧侶たちが祈っていた場所からは随分外れてしまっていた。
もう祈りの声はほとんど聞こえず、ただ物音は己の足音だけという静けさの中で、クラヴィスは神経を研ぎ澄まし、目的の場所に向かって歩くことだけを考えた。回廊の青い壁面が途絶えて、また剥き出しの煉瓦の壁になった時、クラヴィスは中庭か、あるいは、王宮の裏庭にでもつながっているのかと思い、先を急いだ。目の前に、鉄の扉を見つけたクラヴィスは、その中から何かしら自分を呼ぶような声がしたように思い、重い扉を開けた。
「!」
とクラヴィスは立ち尽くす。青一色に統一されたはずの宮であるのに、その部屋は、真紅の壁面で覆われていたからだった。
NEXT |