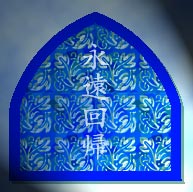|
|
ジュリアスは、中庭に続く回廊の角に頃合いの石造りの長椅子があるのを見つけた。 |
|
鎮魂の祈りを捧げた後、クラヴィスもまたその魂の悲しみを己の中に感じ取り、深く傷つくのだ。 『無念のうちに死んでいった人の悲しみはあまり私には解らぬ……ただクラヴィスが苦しんでいることが私は悲しいと思う……それではいけないのか?』 かつて、そう問いかけた幼いジュリアスに、地の守護聖は微笑んだ。今は、それでいいのだと。鎮魂の時は、ただ光の守護聖である貴方が、側にいるだけでいいのだと。 ジュリアスはその言葉を思い出しながら、クラヴィスの傍らに佇んでいた。意味の解らぬ祈りが穏やかに満ちる中、クラヴィスの苦しみが癒えるように、また彼がどこかに行ってしまわないようにと思いながら、冷たい彼の手を握りしめる。クラヴィスは、まだ朦朧としている意識の中で、その手の温もりを感じていた。 (この手が無ければ、還れなかった……今度もまた……) その言葉はクラヴィスの唇から、微かな呻きとなってジュリアスの耳に届く。 「もう立ち上がれるか?」 まだ座ったままのクラヴィスは、気怠そうにジュリアスを見上げると、立ち上がらせてくれと言わんばかりに、もう一方の手を差し伸ばした。ジュリアスは、クラヴィスの頬に僅かに赤みが戻っているのを確かめた。 「甘えるでない。自分で立つがいい」 「フ……つれないことを言う」 クラヴィスは、ゆっくりと立ち上がる。それでも鎮魂の疲れから目眩を感じて、思わず目を閉じる。 と、同時に、すばやくジュリアスはクラヴィスの背後に回り、その体を支えた。 「すまぬ」 クラヴィスは、目を閉じてジュリアスに支えられながら言う。 「長い間、私はそうやってお前に支えられてきたのだな。お前なしでは、結局、何も出来ない……」 「何を言うのだ。鎮魂は、そなたしか出来ぬこと。私はただ側で見ているだけではないか」 「鎮魂のことだけではない、全てのことを言っているのだ。お前は私より早く生まれて守護聖になった。だがそれは、宇宙の時の流れからみれば、瞬きにも満たないほどの一瞬の差にしかすぎない。古来の記録を見ても光と闇の守護聖は一対で生まれている。だから私は、つかの間の愛よりもお前を選んだ。私は間違っていたか?」 まだクラヴィスの意識は朦朧としていた。いつものクラヴィスにしては、激しい口調だった。唐突でもあった。クラヴィスは、再び腰を石の長板に落とした。ジュリアスはクラヴィスの問いかけに戸惑いながら、その意味を探った。 つかの間の愛の意味が、前女王とのことであるとすぐに気づくと、ジュリアスは俯いた。 「あの時、次代を継ぐべき者と、それを支えるべき守護聖が、共に歩むことを選んだとしたら、この宇宙はどうなっていただろう……。それでも、この宇宙は確かに存在しただろうか? 何の災いもなしに? そなたは、つかの間の愛と言ったが、永遠のものであったかも知れない。そなたたちが愛し合っても、宇宙は平穏でありつづけ、天命尽きるまで、添い遂げたかも知れない。今ならそう考えることも出来る。だが、あの時は、私は……」 言い続けようとするジュリアスをクラヴィスは遮った。 「お前を責めているのではない。誤解するな。結局、私は怖かったのだ。さだめの向こうにあるものを確かめるのが……。だが、時折、光の守護聖のお前の側にいれば、間違いは無いと、安易な選択をした気がして……それは間違っていたのかと、今になって思うのだ」 「クラヴィス、私はそなたが間違ってはいなかったと思う。いや、そう思いたい……まるで自分を肯定しようとしているようだが」 ジュリアスはそう言うと、クラヴィスの隣に腰掛けた。 「ようやく長い呪縛から解放されるというのに、私はそれを恐れている……」 クラヴィスはそう言うと、また瞳を閉じた。 「サクリアが消えれば聖地を去る……皆そうしてきた。聖地に来る前の人としての生活の記憶が、皆はあるからそうするのだろう。そなたもそうだな。だが、私はほとんど何も覚えてはいない。断片的に住んでいた館の様子などを思い出すことはあるが、それは何かの物語の中のことと、混同しているのかも知れない。 はっきりしているのは、聖地から迎えの使者が来た日からのことだけだ。そなたには言おう……私は怖かった。聖地を去る日が来ることと、聖地の平穏を乱すかも知れぬものが。それ故に私は懸命に、光の守護聖であろうとした……」 ジュリアスは長い間封じ込めていた言葉を呟いた。長い旅路の末に辿り着いた旅人が荷物を投げ出すように。 「そして、そなたに去られることも怖い……。少し長じてから、年長の守護聖が一人、また一人と去り、私に、本当の意味での首座の守護聖の任務が求められた時は、私の一番辛い時期だった。そんな時期に女王交代があり、私は一番そなたの力を欲していたのだ。素直にそう言えば良かった。もっとそなたと言葉を交わせば良かったと思っている。そうすれば、私たちは、本当に良き友になれたろうに……」 「私もお前も、長く聖地に居すぎたのかも知れぬな」 クラヴィスは悲しげに言うと、ゆっくりと立ち上がった。今度は目眩は襲って来なかった。しばらくの沈黙の後、クラヴィスは大きく息を吐いた。 「この寺院は、この星にあっては貴重な文化遺産だが、老朽化している。だが修復するだけの予算が、内戦の続いた今の国家に無い。私が全額負担することにした。その代償としてここに住まうことを許可させた」 クラヴィスは、いきなりそう話し出した。 「ほう、そなたにしては手はずの良いことだな……」 「父親の悪行を懺悔してやろうと思ってな。良く出来た息子であろう?」 「そのことを、関係者は理解しているのか?」 「フッ……まさか。ここは主星とは違う。聖地信仰は、異教とされて葬られたところなのだぞ。自分は守護聖だった、二百年ほども前の王が、実は父だったと言って、誰が信じる。それに私はその王が、時折、戯れただけの踊り子から生まれたのだから、記録も何も無い。私とて、母親から聞かされていたにすぎぬからな。だがこの土地が 、私の故郷であることに間違いはない。私は地方の資産家ということにして偽装の戸籍を使いの者に用意させた」 クラヴィスは、その展開を楽しんでいるように言った。 「そなたは、ずっとここに留まるつもりなのか?」 「修復には何十年もかかると言われている。あのタイルに書かれたものに関する資料も不完全だ。私はそれを解読することで、この修復プロジェクトに参加しようと思っている」 「積極的なのだな」 とジュリアスは言った。が、その言葉に(聖地に居た時とは違って……)という揶揄が含まれていることをクラヴィスは、敏感に感じ取った。 「フッ……すまぬな」 「まったくだ」 クラヴィスとジュリアスは、瞳で微笑みあった。 |
|