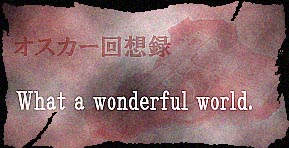
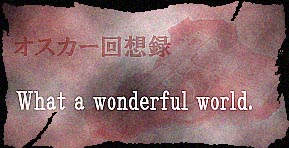
上海行きの二等客船の部屋で俺はずっと酒を飲んでいた。もう何もかも終わりだと、ヤケになっていた。俺は大学を出たばかりの新聞記者で前途揚々、薔薇色の人生が始まるはずだったのに……。『ニューヨークタイムズ上海支局特派員に命ず』……たった一枚の紙切れで、俺は極東に飛ばされたのだった。 飛ばされた理由は、俺が少しばかり中國語が出来たからだけではない。当時付き合っていた女の親父の差し金だった。彼女の親父は金持ちで、手切れ金をもって娘と別れるように俺に迫った。俺はもちろん断った。そうしたら次の週には俺は上海行きの船の上ってわけだ。
しかし上海の暮らしは思ったより悪くはなかった。食べ物も酒も旨い、そして何よりも女性は素晴らしかった。俺は、メイド付きの小綺麗な屋敷に住み、仕事が終わると毎夜遊び歩いた。最初の一年は夢のように過ぎた。
俺の仕事といえば、本国に送る『上海便り』というコラム記事を書く事位で大した事もしていなかった。持て余した体力と仕事への情熱は全て美姑娘や、向こう見ずな貴族のご令嬢とのアバンチュールに費やしたのだった。
こうして上海での二年目の秋が過ぎた頃から、俺は、経済欄の担当になり、仕事も忙しさを増していった。南京路の近くの雑居ビルに住まいとは別に仕事部屋を借り、屋敷に帰れない日が続いた。
この頃から俺は、次第に上海の影の部分を知るようになる。もちろん今までも四馬路の路地を入り込んだところにある妖しげな娼窟や阿片窟、暗い目をしていつまでもしゃがみ込んでいる貧しげな中國人、そういったものは嫌と言う程見てきた。
俺が知った影はもっと上層部分の阿片の密輸に絡んだ汚職……。俺はある政府関係者と公安局員との汚職を突き止めたが、拉致され半殺しの目に遭い、ようやく釈放され帰ってみれば、俺の屋敷は原因不明の火事で跡形もなかった。しかも支局長は俺の書いた記事をボツにし、何も見なかった事にしろと言った。
「後一年我慢しろ、そしたら本国に帰れるんだ。私は後半年で任期が明ける。頼む、トラブルは起こさないでくれ……」
支局長はそう言い、若かった俺は何もかもが汚れて見えて、会社を辞めた。
俺は、仕事部屋の雑居ビルに移り住み、外灘に立ち並ぶ企業から、身元調査や行方不明の積み荷を調べる仕事などを貰ってなんとか生き延びていた。
ニューヨークタイムズの記者をしていた頃とは収入は雲泥の差、今まで出入りしていた倶楽部も除籍され、俺は次第に荒んだ生活に堕ちていった。
★ next ★